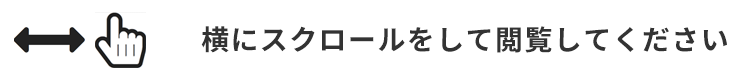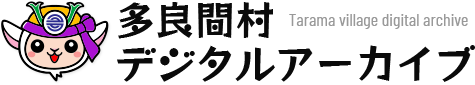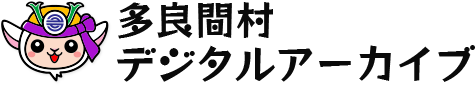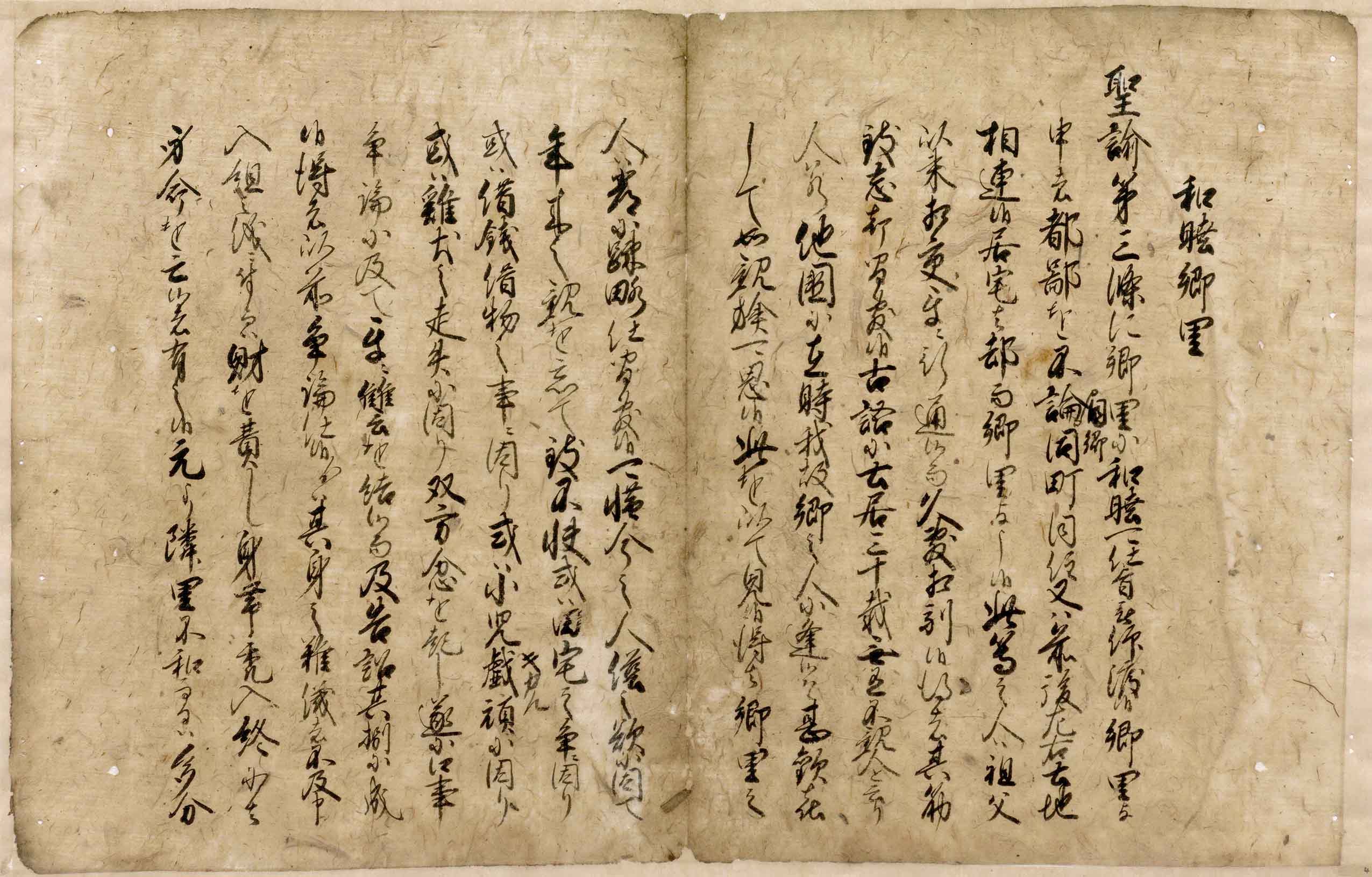5ページ目
- 翻 刻
- 現代語訳
「4
和睦郷里
(台)聖諭第三條に郷里に和睦可仕旨被渡候卿里より
申者都鄙を不論同郷同町同町同住又は前後左右土地
相連候居宅其部而卿里より申候此等之人は祖父
以来相交互に行通候而久敷相馴候得去其筋
致忘却間敷候古語に士居三十載無有不記合と云り
人筋他国に在時我故卿之人に逢候ハゝ甚歡喜
して如親捨可恩候を以て見候得其卿里之
人ハ常に疎略仕間敷候可惜今之人僅之欲に因て
年来之親をして致不快或田宅之争ニ因り
或は借銭借物之事ニ因り或は小児戯頑(ルビ:キカん)に因り
或は鶏犬之走失に因り双方念を起し遂に口事
争論に及て互ニ讐云を結候而及告訟其捌に成
候得者以前争論仕候よりは其身之雑儀は不及申
入組み儀に付ては財を費し身帯禿入終には
身命を云候者有之候元より隣里不和なるは多分
「4
郷里の人々と仲良くすることについて
「聖諭」第三条には、郷里の人々と仲良くするようにと示されている。
ここでいう「郷里」とは、都市か田舎かを問わず、同じ村や町に住む人々のことを指す。また、隣接する土地に住む者たちも含まれる。
こうした人々は、祖父の代から互いに交流し、長い年月をかけて親しくなってきた。
だからこそ、その関係を忘れるべきではない。
昔の言葉に「士(さむらい)は三十年同じ土地に住めば、互いに顔を知らぬ者はいない」とある。
もし遠く他国にいるときに、故郷の知り合いに出会えば、まるで家族に会ったかのように喜び、深く恩を感じるものである。
このことを考えれば、普段から郷里の人々をないがしろにしてはならない。
しかし、残念なことに、今の世の人々は、わずかな欲のために長年の親しい関係を壊してしまうことがある。
たとえば、田畑や家の境界をめぐる争い・借金や物の貸し借り・子ども同士の遊びの喧嘩・鶏や犬が逃げたこと。
こうした些細なことが原因で互いに恨みを持ち、やがて口論や争いに発展し、ついには訴訟にまで至ることがある。
訴訟に発展すると、最初に争った理由よりも、その後の手続きのほうが大きな負担となる。
さらに、財産を失い、生活が困窮し、最悪の場合、命を落とす者さえいる。
そもそも、隣人同士が不和になることは